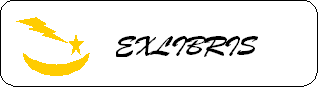人間に対する愛(松浦静山『甲子夜話』)
『松浦静山 甲子夜話』(高野澄編訳 昭和五十三年 徳間書店)を読了した。
松浦静山は平戸藩第三十四代藩主、一風変わった情報マニアだ。甲子夜話は彼の十年以上にわたる見聞の記録簿であり、そのボリュームは正続合わせて二百巻にもおよぶ。平凡社の東洋文庫に全編おさめられているが、今回読んだのは‘人’をテーマとする話を編んだ、いわばダイジェスト版人事編である。
さて、みずからが奇人の代表格たる静山が興味を持ったのはどんな人たちか。
たとえば、袴の裾を自分でくくれない肥前少将の鍋島治茂。外出のたび帰りが遅れて言い訳する家臣に、「おまえたちはいいところがあっていいな。この私には行くところがない」と笑って答えた人。この人の容姿を写した箇所が、いかにも鷹揚・古風な人柄を伝えていてる。『其質、厚篤なることなりき。其容体は、腰をそらせ鳩胸にて、足は棹の如く立て歩する人なり。因って殿中にても、人、其容体をおかしがりたり。又一種の癖あり、手水をせらるる時、湯次の水(手洗いの水)を何遍となく替るほど長く為られたり。』――いい文章だ。特に手水の時の癖を加えたのが効いている。
また、庭中で家来と共に水鉄砲を持ち、知合いの太鼓打を追いかけまわした、備前岡山藩の松平一心斎。
浄瑠璃の本を見台に載せ、経書講義を暗誦で行った、徂徠門下の筑波山人。
春の凧上げが趣味で、夜になっても、煙草をふかしながら息子と星空に凧をあげていた、御具足奉行の本山七蔵。
他に、怪盗‘鼠小僧’も出てくるし、世人の不評を蒙った老侯の邸門に描かれた卑猥な落書、あるいは不幸にして罪に落ちた知人のことも、静山は極力私情をまじえず、時事報告のような調子で書き留めている。いくら好奇心旺盛でも、十年以上、これだけ高く感性のアンテナを掲げつづけるのは容易なことではない。いったい何が、静山の耳目を機動さすエネルギーとなったのだろう。
ちなみに自分は‘愛’という文字を使うのを好まない。文字や言葉そのものが嫌いなのではなく、歌でも、詩でも、小説でも、昨今の軽々しい、まるで犬猫の交尾の理由づけじみた‘愛’の用いられ方に、嫌悪と反発を感じているからだ。
しかし、こと静山の場合に限っては、他でもない、「人間に対する無差別な愛」が、彼を情報収集へと駆りたてる衝動の源ではないかと言いたくなる。
彼は根本から人間が好きだった。根本から人間を信じていた。その証拠に、罪に怒っても、罪せらるる人そのものを責めたりしていない。長く他人に接すると、最初に尊敬の念がきて、あとはひたすら失望の思いがまさりゆく、これが人づきあいにおけるお決まりのパターン。それゆえ、世の中を見つめすぎた人ほど、とかく人間嫌いに陥りがちだ。ところが静山の語り口からは、厭世観・厭人観というものが露ほどもうかがえない。
先ほど引用した鍋島治茂の容姿を写した箇所などは、伝聞を淡々と述べてはいても、人を見つくし、知りつくしたのちになお湧きおこる思慕敬愛の念にあふれている。人間自体を愛しきる先天的な資質、それがなければやはり、甲子夜話の著述は、早々に投げ出されてしまう仕事であったにちがいない。
そんな静山が、めずらしく怒りを露わにしたのが、泰平の大阪城内にかっての合戦の響きがすると聞き、その事実を問い合わせた時の話。前に大阪に滞在した人の「其事知らず」という返答を、静山は「心無き輩は何事も気の付かぬにや」という寸評で一蹴している。
短く手きびしい言葉だ。そして「こころない」の本来の意味が、とてもよく分かる例でもある。
|